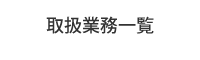虎ノ門法律経済事務所神戸支店、弁護士の村木です。
ご相談の多い「離婚問題」について、数多くの判決事例の中から4件ご紹介します。
今回は「協議離婚届出書を作成後にやはり離婚をしたくないと気持ちが変わり、その後相手が勝手に届出書を提出したら受理されるのか」「夫婦の一方が病気を患ったら、病気を理由に離婚ができるのか」「別居期間が長いとどうなるのか」というケースです。
協議離婚届出書を作成後に協議離婚を翻意し、その後相手が届出書を提出しても、その届出は無効であるとした事例(最判昭和34年8月7日)
本件協議離婚届書を作成後、X男は市役所係員に対し、離婚届が出されるかもしれないが、離婚を承諾したものではないから受理しないでほしい旨申し出でたこと、および、X男は右届出のあった前日、協議離婚の意思を翻していたことが認められる。
「そうであるとすれば、Y女により届出がなされた当時にはX男に離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。」
そして、必ずしも「右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかったからといって、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。」
「そうであるとすれば、Y女により届出がなされた当時にはX男に離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。」
そして、必ずしも「右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかったからといって、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。」
夫婦の一方が不治の精神病にかかった場合でも、病者の今後の療養・生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度その方途の見込みのついた上でなければ、婚姻関係を廃絶することはできないとした事例(最判昭和33年7月25日)
民法770条は、あらたに『配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないとき』を裁判上離婚請求の一事由としたけれども、同条2項は、右の事由があるときでも裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであって、民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。
不治とはいえない精神病の妻に対する離婚請求は、療養・生活につき具体的方途を講じていなくても認められるとした事例(東京地判昭和42年11月29日)
「妻は、精神分裂病に罹患し」「保養院に入院し、その間、電撃療法あるいは薬物療法、その他専門的生活指導のほか、退院後も精神医学的管理のもとになされる社会復帰のためのナイトホスピタルの施行等もうけ、最近は、右治療等により軽快しかなりの安定状態にあること、今後なお当分の間は精神医学的管理のもとに置かなければ既往からみて再発の危険がないとはいえないが、精神分裂病の欠陥状態にある者相応の能力に応じ要素的な意味での家庭生活を営むことは不可能ではないことが認められる。」
「民法第770条第1項第4号は配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないばあいを離婚原因と定めているが、本件では、回復の見込なきものとは認めることができないから、右を離婚原因とする請求は理由がない。」
(もっとも、本件では、婚姻の破綻について、原被告いずれの努力をもってしても容易に克服しえない諸要素が強く支配した情況が認められるなどとして、民法第770条第1項第5号を離婚原因とする離婚請求は認容できるとした)
「民法第770条第1項第4号は配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないばあいを離婚原因と定めているが、本件では、回復の見込なきものとは認めることができないから、右を離婚原因とする請求は理由がない。」
(もっとも、本件では、婚姻の破綻について、原被告いずれの努力をもってしても容易に克服しえない諸要素が強く支配した情況が認められるなどとして、民法第770条第1項第5号を離婚原因とする離婚請求は認容できるとした)
有責配偶者からの離婚請求において、8年間の別居が「相当の長期間に及んだもの」とされた(最判平成2年11月8日)
有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約8年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比に置いて別居期間が相当の長期に及んだと解すべきである。